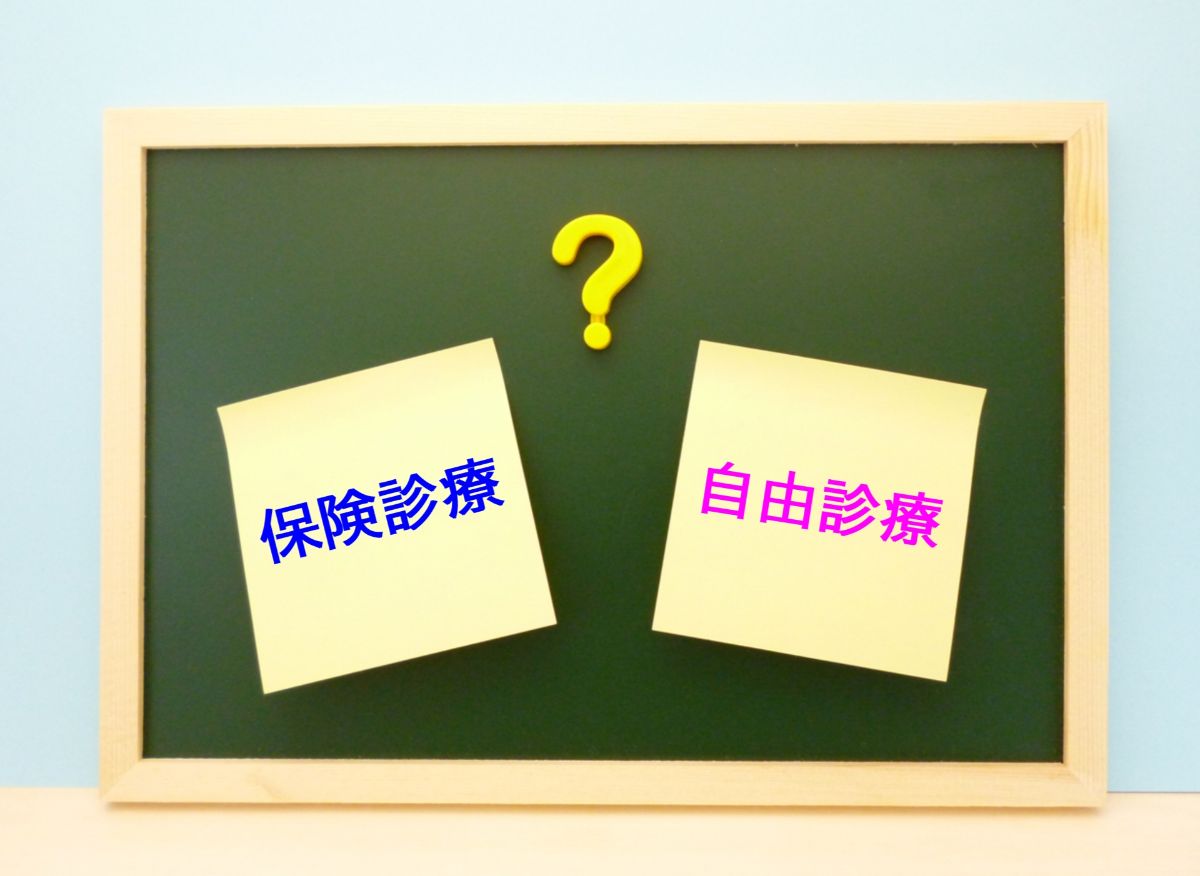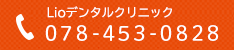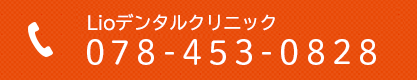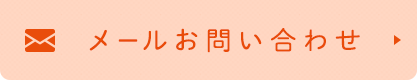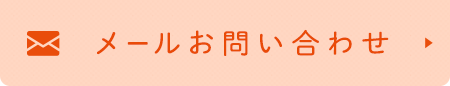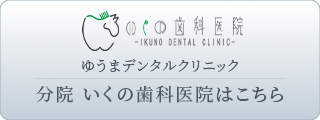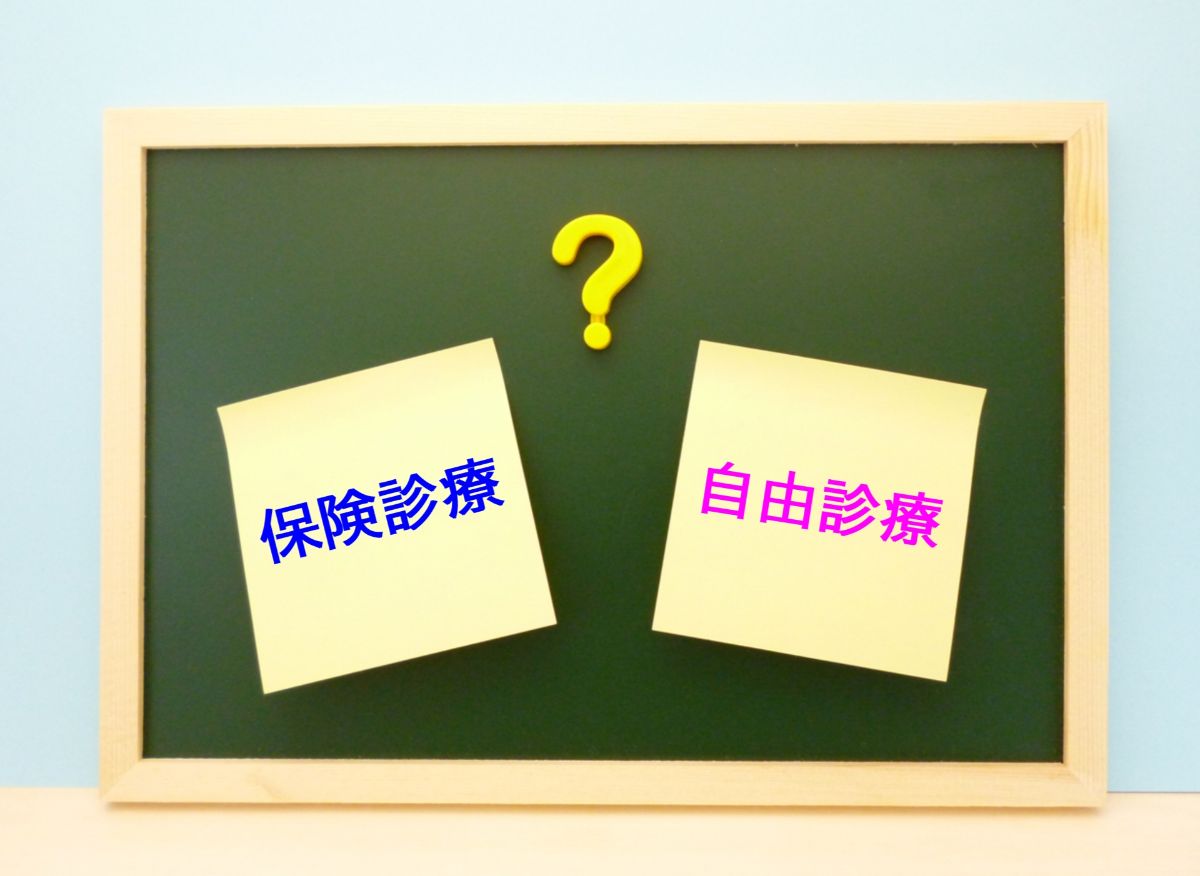
インプラント治療を検討している方にとって、保険適用の有無は非常に重要なポイントです。一般的にインプラントは自由診療とされ、1本あたりの治療費は30万円~40万円、場合によっては100万円を超えることもあります。しかし、特定の条件を満たせば、健康保険が適用されるケースも存在します。そういった場合、自己負担額が大幅に軽減される可能性があります。
また、大学病院などの大規模な医療機関では、保険適用のインプラント治療を提供しているところもあります。しかし、待機期間が長い、予約が取りづらいといったデメリットも存在し、すぐに治療を受けたい方には不向きな場合があります。そのため、自由診療と保険診療の違いや、それぞれのメリット・デメリットを理解し、最適な選択をすることが重要です。
さらに、インプラント治療には「医療費控除」を活用することで、年間の医療費が一定額を超えた場合に、確定申告を通じて税金の一部が還付される制度もあります。加えて、一部の民間医療保険では、手術給付金や入院給付金が適用されるケースもあるため、自身の保険内容を確認することも大切です。
この記事では、インプラントの保険適用条件や費用の詳細、自由診療との違い、さらには厚生労働省の見解や今後の制度改正の可能性についても詳しく解説します。保険適用の最新情報を知りたい方、費用を抑えるための方法を探している方は、ぜひ最後までご覧ください。
インプラントやインビザラインならLioデンタルクリニック
Lioデンタルクリニックは、患者様一人ひとりに合った最適な治療をご提供し、安心して通える環境を整えています。一般歯科から矯正歯科、インプラント、インビザライン、審美歯科まで幅広い診療科目に対応し、最新の医療技術と設備を導入しています。患者様の笑顔と健康を第一に考え、丁寧なカウンセリングと質の高い治療を心掛けています。歯のことでお困りの際は、ぜひLioデンタルクリニックへご相談ください。
| Lioデンタルクリニック |
| 住所 |
〒658-0022兵庫県神戸市東灘区深江南町1丁目12−16 光南ハイツ |
| 電話 |
078-453-0828 |
お問い合わせ
インプラントが保険適用される条件とは?具体的な適用範囲と注意点
健康保険が適用されるインプラントの条件
インプラント治療は基本的に自由診療に分類され、全額自己負担となることが一般的です。
しかし、一部のケースでは健康保険が適用されることがあります。健康保険が適用される主な条件は、患者の病状や治療の目的によります。
まず、先天的または後天的な疾患や事故によって顎の骨が広範囲にわたって欠損している場合、健康保険の適用が可能です。例えば、上顎や下顎の広範囲な骨欠損があり、入れ歯やブリッジが適用できないケースなどが該当します。
また、厚生労働省が指定する特定の医療機関での治療に限られる点も重要です。
一般的な歯科医院ではなく、大学病院や特定の口腔外科を備えた医療機関で治療を受ける必要があります。これにより、健康保険の適用範囲が非常に限定されていることがわかります。
以下は、健康保険適用となるインプラント治療の条件です。
| 条件 |
内容 |
| 先天性欠如 |
生まれつき歯がない場合 |
| 外傷による歯の喪失 |
事故や病気で歯が失われた場合 |
| 広範囲な顎の骨欠損 |
ブリッジや入れ歯の適用が困難なケース |
| 指定医療機関での治療 |
厚生労働省が認める病院のみ |
健康保険が適用されるケースはかなり限られているため、自身が対象となるかを事前に確認することが重要です。また、医師の診断を受け、適用の可否を判断してもらうことが求められます。
自由診療のインプラントとの違い
インプラント治療は、保険診療と自由診療の2つに大きく分けられます。
自由診療の場合、患者のニーズに応じた最適な治療が可能ですが、費用負担が大きいという特徴があります。
一方、健康保険適用のインプラント治療は、適用される条件が厳しく、使用できる材料や治療方法が制限されることが特徴です。
以下に、自由診療と保険診療の主な違いについてまとめました。
| 項目 |
自由診療 |
保険診療 |
| 費用 |
全額自己負担 |
一部保険適用 |
| 使用できる材料 |
高品質なチタンやセラミックなど |
保険適用の標準素材 |
| 治療方法 |
最新の技術や個別にカスタマイズ |
決められた手法に限定 |
| 審美性 |
見た目の美しさも重視可能 |
基本的な機能回復が目的 |
自由診療では、歯の色や形を細かく調整できるセラミック素材を選べるなど、見た目の美しさを考慮した治療が可能です。
逆に、保険適用の場合は、機能回復を目的とし、見た目よりも治療効果を重視するため、選択肢が制限されることになります。
また、自由診療では最新技術を用いた手術が可能ですが、保険適用の治療は医療機関によって手法が統一されるため、治療の選択肢が限られる点に注意が必要です。
保険適用インプラントの治療の流れ
健康保険適用のインプラント治療を受けるには、いくつかのステップを踏む必要があります。
通常の自由診療のインプラントと比較して、事前の診断や手続きが厳格に定められていることが特徴です。
以下は、保険適用インプラント治療の流れです。
| ステップ |
内容 |
| 1.初診・検査 |
口腔内の状態を確認し、保険適用の可否を判断 |
| 2.診断書の作成 |
保険適用の条件に該当するかを診断 |
| 3.申請手続き |
指定医療機関にて保険適用の申請 |
| 4.手術 |
保険適用の治療手順に沿ってインプラントを埋入 |
| 5.メンテナンス |
治療後の経過観察とメンテナンス |
保険適用のインプラント治療を受けるためには、厚生労働省が定める基準を満たしているかどうかの診断を受ける必要があります。通常、診断の結果、保険適用が認められた場合にのみ手術が可能となります。
また、健康保険適用のインプラント治療では、手術後のメンテナンスが必須となります。適切なケアを怠ると、インプラントの寿命が短くなるため、定期的な診察を受けることが推奨されます。
このように、健康保険適用のインプラント治療には厳しい条件があるため、事前に適用範囲や治療の流れを理解しておくことが重要です。自由診療と比較しながら、自分に最適な治療方法を選択することが望ましいでしょう。
なぜインプラントは保険適用外?その理由と背景
日本の公的医療保険制度の仕組み
日本の公的医療保険制度は、国民全員が一定の医療を受けられるように設計されています。
健康保険や国民健康保険を利用することで、多くの医療費の自己負担を抑えることが可能です。
しかし、すべての治療が保険適用になるわけではなく、公的医療保険が適用されるかどうかは「必要性」と「治療の目的」によって判断されます。
日本の健康保険制度では、病気や外傷によって機能が失われた場合の治療は保険適用の対象となります。
例えば、虫歯や歯周病の治療、入れ歯やブリッジによる欠損歯の補綴は保険診療に含まれます。しかし、機能回復だけでなく、美容や審美目的の治療は保険適用外となることが原則です。
以下は公的医療保険が適用される歯科治療の分類です。
| 治療内容 |
保険適用の有無 |
| 虫歯治療(詰め物・被せ物) |
保険適用 |
| 歯周病治療 |
保険適用 |
| 抜歯(親知らず含む) |
保険適用 |
| 部分入れ歯・総入れ歯 |
保険適用 |
| ブリッジ治療 |
保険適用 |
| インプラント治療 |
保険適用外(※例外あり) |
| セラミッククラウン |
保険適用外 |
| ホワイトニング |
保険適用外 |
インプラント治療が公的保険の対象とならない主な理由は、「自由診療」に分類されるためです。
インプラントは従来の入れ歯やブリッジに比べて、審美性が高く、より自然な噛み心地を得られる治療ですが、国が定める標準治療の範囲外であるため、基本的には保険適用外となります。
保険適用外のケースとその対策
インプラントが保険適用外となるケースには、いくつかの具体的な理由があります。
基本的に、通常の歯科治療でカバーできる治療方法がある場合は、保険適用の対象外となるという原則があるためです。
以下は、インプラントが保険適用外となる主なケースです。
| ケース |
理由 |
| 虫歯や歯周病で歯を失った場合 |
ブリッジや入れ歯で対応可能なため |
| 加齢により歯が抜けた場合 |
入れ歯の選択肢があるため |
| 美容目的でインプラントを希望する場合 |
機能回復が目的でないため |
| インプラントの種類を選びたい場合 |
保険適用の場合は制限があるため |
しかし、一定の条件を満たす場合に限り、インプラントが保険適用となるケースもあります。
例えば、先天性疾患や事故などで顎の骨が広範囲に損傷している場合には、公的医療保険の対象となることがあります。
保険適用が受けられない場合の対策として、以下のような対策を取ると負担が減るかもしれません。
- 医療費控除を活用する
インプラント治療は高額ですが、年間の医療費が10万円を超えた場合、確定申告を行うことで医療費控除を受けることができます。通院にかかった交通費も対象となるため、適用範囲をしっかり確認しましょう。
- 分割払い・デンタルローンの活用
多くの歯科医院では、治療費を分割で支払えるデンタルローンを導入しています。月々の負担を軽減しながら治療を受けることが可能です。
- クリニック独自の割引制度を利用
一部の歯科医院では、複数本のインプラント治療を受ける際に、まとめ割引が適用されることがあります。事前に医院に確認すると良いでしょう。
民間保険でカバーできる範囲とは?
インプラント治療が公的医療保険でカバーされない場合、民間の医療保険や生命保険で補償を受けることができるケースがあります。特に、手術給付金が支払われるタイプの医療保険や、歯科治療特約が付帯している保険が該当します。
| 保険の種類 |
適用範囲 |
| 医療保険(手術給付金あり) |
インプラント手術が対象となる場合あり |
| 生命保険(手術特約付き) |
手術の内容に応じた給付金を受け取れる |
| 歯科治療専用保険 |
一部のプランでインプラントを補償対象に含む |
| がん保険 |
口腔がん治療によるインプラントで適用される場合あり |
ただし、民間保険でカバーされるかどうかは、契約内容によって異なります。
保険加入時に「歯科治療が補償の対象になっているか」をしっかり確認することが重要です。また、既にインプラント治療を受けた後では、加入ができない場合があるため、事前に検討しておく必要があります。
さらに、高額医療費制度の対象にはならないため、治療費全額を自己負担しなければならない点にも注意が必要です。
民間保険を利用する場合は、自分の契約内容と治療の適用範囲をしっかり確認し、歯科医院と相談の上で活用するのが賢明な方法です。
今後インプラントは保険適用になるのか?将来の展望と可能性
過去の保険適用の変遷と制度改正
インプラント治療が日本で普及し始めたのは1983年以降ですが、当初は完全に自由診療として扱われていました。
しかし、近年になって一部の条件下では保険適用されるようになりました。これは、患者の経済的負担を軽減するために行われた制度改正の一環です。
日本の健康保険制度では、治療が「機能回復を目的とするもの」であるかどうかが保険適用の基準となります。
そのため、従来は入れ歯やブリッジなどの代替手段が存在する限り、インプラントは保険適用外とされてきました。しかし、2012年に制度改正が行われ、先天性欠損症や外傷による顎の広範囲な欠損がある場合に限り、インプラントが健康保険の対象となりました。
過去の制度改正を振り返ると、インプラントが保険適用される範囲は少しずつ拡大していることが分かります。
しかし、現時点では特定の症例に限られており、一般的なケースでは依然として自由診療の扱いとなっています。
今後インプラントが保険適用になる可能性
将来的にインプラント治療がより広範囲で保険適用される可能性は十分にあります。
これは、日本の高齢化社会の進行や、インプラント治療の普及率の向上によるものです。特に、高齢者の増加に伴い、入れ歯よりも快適な治療法としてインプラントの需要が高まっているため、国としても保険適用の拡大を検討する必要が出てきています。
以下に、インプラントの保険適用が拡大される可能性の要因をまとめました。
| 要因 |
具体的な影響 |
| 高齢化の進行 |
入れ歯よりもインプラントを希望する高齢者が増加 |
| インプラント技術の進化 |
低コストで安全な治療が可能になってきている |
| 海外の事例 |
一部の国では保険適用が拡大されている |
| 健康寿命の延長 |
より快適な咀嚼機能の回復が求められる |
特に、スウェーデンやドイツなどの一部の欧州諸国では、インプラント治療の一部が公的保険の対象となっています。これは、インプラントが入れ歯よりも長期的な健康維持に貢献するという考え方があるためです。
日本でも、今後の制度改正によって特定の条件下でインプラントの保険適用範囲が拡大される可能性があります。例えば、高齢者や重度の歯周病患者に対するインプラント治療を限定的に保険適用とする制度の導入などが考えられます。
歯科業界や専門家の見解
歯科業界や専門家の間では、インプラントの保険適用拡大には賛否両論があるのが現状です。
一部の専門家は、インプラント治療が咀嚼機能の回復において非常に有効であり、公的保険での適用範囲を広げるべきだと主張しています。
一方で、保険適用を拡大すると治療の質の低下や、医療財政の逼迫が懸念されるという意見もあります。
| 立場 |
主張内容 |
| 保険適用を拡大すべき |
咀嚼機能の回復効果が高く、QOL(生活の質)向上に貢献する |
| 限定的に適用すべき |
高額な治療のため、全体に適用すると財政負担が大きい |
| 反対意見 |
保険適用にすると、低価格の素材しか使えなくなり治療の質が下がる可能性 |
現在のところ、日本の厚生労働省は慎重な姿勢を取っており、短期間での全面的な保険適用拡大は難しいと考えられます。
しかし、今後の医療財政の状況や技術革新の進展により、部分的な適用範囲の拡大は十分にあり得るでしょう。
インプラント治療の保険適用は、今後の高齢化社会の進行や治療技術の向上によって拡大される可能性があります。
しかし、財政負担や治療の質を維持するためには慎重な議論が必要です。現在の制度では、特定の症例に限り保険適用が認められているため、自身の治療が対象となるかどうかを事前に歯科医と相談することが重要です。
将来的には、部分的な保険適用の拡大が期待されるものの、全面適用には時間がかかる可能性が高いといえます。
インプラント治療の保険適用について厚生労働省の公式見解
厚生労働省が定めるインプラント治療の保険適用基準
厚生労働省は、日本の医療保険制度における治療の適用範囲を定める機関であり、インプラント治療に関しても特定の基準を設けています。
一般的にインプラント治療は自由診療に分類され、患者が全額自己負担する必要がありますが、特定の条件下では健康保険が適用されるケースもあります。
インプラント治療が保険適用される主な条件は以下の通りです。
| 適用条件 |
詳細 |
| 先天性欠損 |
先天的に永久歯が欠如している場合 |
| 外傷による歯の喪失 |
交通事故やスポーツ事故などで歯を失った場合 |
| 顎骨の広範囲な欠損 |
腫瘍の切除や病気により大きな骨欠損が生じた場合 |
| 指定医療機関での治療 |
厚生労働省が認可した医療機関のみで適用 |
このように、生まれつきの欠損や外傷による大きな骨の喪失がある患者に限り、健康保険が適用される仕組みになっています。
しかし、虫歯や加齢による歯の喪失の場合は、従来の入れ歯やブリッジによる治療が可能とされ、保険適用の対象外となります。
また、保険適用のインプラント治療を受けるためには、治療を行う医療機関が厚生労働省の指定を受けていることが条件となります。これは、適切な治療が行われることを保証するための措置であり、一般的な歯科医院では保険適用のインプラント治療を行うことができません。
保険診療のルールと適用範囲
健康保険を適用したインプラント治療には、特定のルールが存在します。
これは、保険財政を適正に管理し、必要な患者に適切な医療を提供するための規定です。
以下に、保険診療の基本ルールと適用範囲をまとめます。
| ルール |
内容 |
| 適応症の制限 |
特定の疾患や外傷に限る |
| 指定医療機関 |
厚生労働省が認めた病院でのみ実施可能 |
| 使用する材料 |
保険適用の範囲内で決められたもののみ |
| 費用負担 |
一般的には治療費の30%を患者が負担 |
このように、保険適用のインプラント治療は、非常に厳格なルールのもとで行われるため、自由診療と比較すると使用できる材料や治療方法に制限があることが特徴です。
たとえば、保険診療では、インプラントの材質やメーカーが限られるため、審美性や機能性にこだわる場合には自由診療を選択する必要があるでしょう。
また、保険診療では定められた手順に沿った治療しか行えないため、患者の個別ニーズに対応する柔軟性が低いことも特徴です。
そのため、より高度な治療や最新技術を希望する場合は、自由診療を選択することが推奨されます。
今後の制度改正に関する発表
厚生労働省は、医療制度の見直しを定期的に行っており、インプラント治療の保険適用拡大に関する議論も進められています。
現在の制度では一部の症例にしか保険適用が認められていませんが、今後の高齢化社会の進展や技術の進歩により、保険適用範囲の拡大が期待されています。
今後の制度改正の方向性について以下にまとめました。
| 改正の可能性 |
期待される内容 |
| 適用範囲の拡大 |
重度の歯周病患者や高齢者にも適用される可能性 |
| 材料の選択肢拡大 |
保険適用でも高品質なインプラントが使用可能になるか検討 |
| 自由診療との併用 |
一部の自由診療の要素を組み込みながらの治療選択 |
| 医療機関の増加 |
指定医療機関を拡大し、受診しやすくする |
特に、高齢化の進展により、インプラントの需要が急増しているため、保険適用を拡大するべきだという意見が増えているのが現状です。
現時点では、自由診療が主流のインプラント治療ですが、将来的には公的な補助がより充実する可能性が高いでしょう。
また、咀嚼機能の向上が健康寿命の延長につながるという観点から、政府もインプラント治療の重要性を認識しつつあります。そのため、一定の条件下での保険適用が拡大される可能性は十分に考えられます。
厚生労働省の公式見解では、現時点では特定の症例に限りインプラントの保険適用が認められているものの、将来的には適用範囲の拡大が検討される可能性があることが示唆されています。
インプラント治療は自由診療が主流ですが、今後の制度改正によって、より多くの人が負担を抑えながら治療を受けられる時代が来るかもしれません。
現在の制度では、自由診療と保険診療のどちらを選択するかを慎重に検討することが重要です。自身の治療が保険適用に該当するかどうかを知るためにも、歯科医としっかり相談し、最適な治療方法を選ぶことが大切でしょう。
大学病院でインプラント保険適用のメリットとデメリット
大学病院での治療の流れと特徴
大学病院でのインプラント治療は、一般の歯科医院とは異なる特徴を持っています。
特に、保険適用のインプラント治療が受けられる施設として、一部の大学病院が指定されているため、これを活用することで治療費の負担を軽減できる可能性があります。
ここでは、大学病院での治療の流れとその特徴を詳しく解説します。
以下に、大学病院でのインプラント治療の流れをまとめました。
- 初診・カウンセリング
- 口腔内の状態を詳しく診断し、インプラントが適用できるかを評価
- 必要に応じてレントゲンやCT撮影を実施
- 診断・治療計画の立案
- 顎骨の状態や周囲の歯の健康状態を確認し、治療方針を決定
- 保険適用が可能かどうかを判断し、必要な手続きを案内
- インプラント埋入手術
- 局所麻酔のもとでインプラントを顎の骨に埋め込む
- 手術後は一定期間、骨との結合を待つ(通常3〜6ヶ月)
- 人工歯(上部構造)の装着
- 骨との結合が確認されたら、人工歯を装着
- 噛み合わせの調整を行い、機能回復を図る
- 定期的なメンテナンス
- インプラントが長持ちするよう、定期的な検診とクリーニングを実施
大学病院では、最新技術を取り入れた治療が受けられるだけでなく、インプラント治療の研究が行われているため、より専門的な治療を受けることができます。
また、複雑な症例や難しいケースに対応できるのも大学病院の大きな強みです。
保険適用インプラントを大学病院で受けるメリット
大学病院で保険適用のインプラント治療を受けることには、経済的なメリットと治療の質の向上という二つの大きな利点があります。
経済的メリット
一般的に、インプラント治療は自由診療のため1本あたり30〜40万円かかります。
しかし、保険適用の条件を満たせば治療費の自己負担額を3割程度に抑えることが可能です。
大学病院での保険適用インプラントは自由診療と比べて大幅に費用を抑えることができるのが最大のメリットです。
また、大学病院には専門医が多く、治療の質の向上が期待できます。
- 口腔外科医・歯科専門医による治療
- 高度な技術を持つ専門医が治療を担当するため、より安全で確実なインプラント治療が受けられる。
- 設備の充実
- 大学病院にはCTスキャンや最新の治療機器が揃っているため、精度の高い診断と治療が可能。
- 研究機関としての役割
- 大学病院では最新の研究が行われており、新しい治療法やインプラント技術の開発が進んでいる。
待機期間や予約の取りづらさといったデメリット
大学病院は専門的な治療を受けられる反面、予約が取りづらいことが一般的です。特に、保険適用のインプラント治療を希望する患者が多いため、予約待ちの期間が長くなることがあります。
| 要素 |
影響 |
| 予約の取りづらさ |
1ヶ月以上の待機が必要な場合も |
| 治療開始までの期間 |
予約から診察まで数週間〜数ヶ月 |
| 手術後の待機期間 |
骨と結合するまで3〜6ヶ月 |
インプラント治療は顎の骨とインプラントが結合するまで数ヶ月を要するため、すぐに治療が完了するわけではありません。
さらに、大学病院では研修医や研究生が治療に関わることがあるため、一般の歯科医院と比べると治療スケジュールが長くなる傾向があります。
また、大学病院の保険適用インプラント治療では、使用できるインプラントの種類や治療法に制限があるため、自由診療に比べて選択肢が限られる点にも注意が必要です。
例えば、審美性の高いジルコニアインプラントや、高度な骨造成手術は保険適用外となるため、希望する治療が受けられない場合もあります。
大学病院でのインプラント治療は、費用を抑えながら専門的な治療を受けられるという大きなメリットがあります。
しかし、予約の取りづらさや治療期間の長さ、保険適用による治療の制限などのデメリットもあるため、事前に十分な情報収集を行い、自分に合った治療方法を選択することが重要です。どの治療法を選ぶかは、費用・治療期間・審美性・機能性を総合的に考慮し、歯科医師と相談しながら決定することをおすすめします。
まとめ
インプラントの保険適用については、多くの人が関心を寄せる重要なテーマです。本記事では、インプラント治療の保険適用条件、費用の違い、大学病院での治療の流れやメリット・デメリットなどについて詳しく解説しました。インプラントは、歯を失った際の機能回復のための優れた治療法ですが、現在の日本ではほとんどのケースで自由診療となり、高額な費用がかかるのが現状です。
保険適用となるケースは限られており、先天性欠損や事故による顎骨の欠損など、特殊な条件を満たす場合に限られています。そのため、一般的な虫歯や歯周病による歯の喪失では保険適用されません。その一方で、保険適用の条件を満たせば、治療費の自己負担を大幅に軽減できるため、インプラントを検討している方は、事前に歯科医師としっかり相談し、適用可能かどうかを確認することが重要です。
また、大学病院での治療には、専門的な設備や高度な技術を持つ医師のもとで治療を受けられるというメリットがあります。しかし、その一方で予約が取りにくい、治療に時間がかかるなどのデメリットも存在するため、自身のライフスタイルや治療の優先順位を考えながら選択する必要があります。
さらに、インプラント治療は一度行えば終わりではなく、治療後のメンテナンスが非常に重要です。定期的な歯科検診を受けることで、インプラントの長期的な安定性を保ち、健康的な口腔環境を維持することができます。そのため、インプラント治療を検討している方は、治療後のアフターケアについても十分に理解し、適切なメンテナンスを行うことを心がけることが大切です。
今後、インプラントの保険適用範囲が拡大される可能性もあります。高齢化が進む中で、咀嚼機能の維持が健康寿命の延長に寄与するという研究が進められており、インプラントの必要性がますます高まることが予想されます。そのため、最新の医療制度の変更や保険適用に関する情報を定期的にチェックし、自分に最適な治療方法を選ぶための知識を深めていくことが重要です。
インプラント治療を検討する際は、経済的な負担、治療の選択肢、保険適用の有無など、さまざまな要素を考慮しながら、信頼できる歯科医師と相談し、自身に合った治療計画を立てることが最も大切です。本記事が、読者の皆さまのインプラント治療の選択において有益な情報となれば幸いです。
インプラントやインビザラインならLioデンタルクリニック
Lioデンタルクリニックは、患者様一人ひとりに合った最適な治療をご提供し、安心して通える環境を整えています。一般歯科から矯正歯科、インプラント、インビザライン、審美歯科まで幅広い診療科目に対応し、最新の医療技術と設備を導入しています。患者様の笑顔と健康を第一に考え、丁寧なカウンセリングと質の高い治療を心掛けています。歯のことでお困りの際は、ぜひLioデンタルクリニックへご相談ください。
| Lioデンタルクリニック |
| 住所 |
〒658-0022兵庫県神戸市東灘区深江南町1丁目12−16 光南ハイツ |
| 電話 |
078-453-0828 |
お問い合わせ
よくある質問
Q.インプラントの保険適用条件は何ですか?
A.インプラントが保険適用されるのは、先天的な欠損や事故による顎骨の欠損がある場合、または特定の疾患による歯の欠損が認められたケースです。健康保険が適用されるには、厚生労働省が定める基準を満たす必要があり、例えば大学病院や指定された医療機関での治療が求められます。一方、通常の虫歯や加齢による歯の欠損の場合は、保険適用外となり、自由診療となります。
Q.保険適用のインプラントと自由診療の違いは何ですか?
A.保険適用のインプラントは、必要最低限の治療を対象とし、治療費が抑えられます。例えば、1本あたりの自己負担額は総額の3割程度で済むことが多いです。一方、自由診療のインプラントでは、使用する材料や治療法の選択肢が広がり、審美性や耐久性に優れたセラミックやジルコニアなどを使用できますが、費用は1本あたり30万円~50万円、場合によっては100万円を超えることもあります。
Q.大学病院でのインプラント治療はどんなメリットとデメリットがありますか?
A.大学病院でのインプラント治療は、経験豊富な専門医が対応し、高度な医療設備が整っているため、安心感があります。また、保険適用の対象となる可能性が高く、自由診療よりも費用を抑えられることが大きなメリットです。ただし、デメリットとしては、初診から手術までの待機期間が長く、数か月~1年以上かかる場合もあります。また、予約が取りづらく、定期的な通院が必要になるため、スケジュール調整が求められます。
医院概要
医院名・・・Lioデンタルクリニック
所在地・・・〒658-0022 兵庫県神戸市東灘区深江南町1丁目12−16 光南ハイツ
電話番号・・・078-453-0828